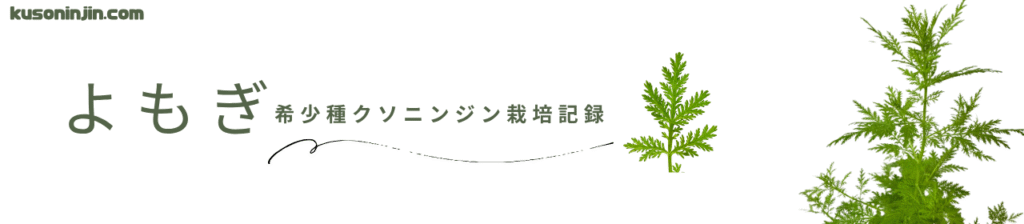クソニンジンとは

ヨモギは健康食として馴染み深い植物です。
「クソニンジン」という強烈な和名を持つこの植物は、キク科ヨモギ属に分類される越年草(または一年草)です。その名前から想像されるイメージとは裏腹に、古来から重用されてきた伝統的な薬草であり、現代医学においてもノーベル賞受賞の鍵となった世界的に極めて重要な存在です。
近年さらなる薬効が期待され、新薬の研究開発が進められています。名前からは想像できない爽やかな香り、欧米ではハーブティーやサプリメントとしても利用されています。
1700年以上の時を経て、近年注目されている植物です。
基本情報
| 名称 | 詳細 |
| 和名 | クソニンジン(糞人参) |
| 学名 | Artemisia annua |
| 生薬名・中国名 | 黄花蒿(オウカコウ)、青蒿(セイコウ) |
| 英名 | Sweet Annie, Sweet Sagewort |
クソニンジン(糞人参)の学名は Artemisia annua(アルテミシア・アヌア)で、中国名では「黄花蒿(オウカコウ)」や「青蒿(セイコウ)」と呼ばれます。諸説あるものの「月の女神アルテミスに由来するアルテミシア」。欧米では香り高いハーブティーとして、美容健康のサプリメントや精油として親しまれています。アルテミシアは月の女神アルテミスに由来するそうです。臭くて嫌われそうな和名とは正反対なのです。

なぜクソニンジン?
①全体に特異な臭気があることから名付けられた。
②葉が細かく羽状に深く裂け、ニンジンの葉に似ていることから付けられた(①②ともに諸説あり)
もともとアジアから東欧にかけて広く分布し、日本では江戸時代以前に薬用として中国から渡来・帰化しました。繁殖力旺盛のヨモギは多年草ですが、クソニンジンは1年草。この1年草という特性が希少種になってしまった原因かもしれません。ベランダに置いて窓を開けておくと、風が吹いた時に葉が擦れ合って特有の爽やかな香りが室内に漂ってきます。ミントとティーツリーを足して薄めた様な爽やかな香りで、花が開花するまでは室内で栽培すると森の中にいるような清々しい香りが広がります。短日植物のため、日照時間が短くなる頃に花を咲かせる準備を始めます。開花すると大量の花粉が舞い散るため、室内での栽培は開花直前までが理想です。


古来からの伝統的な利用と薬効
クソニンジンは、その強い匂いにもかかわらず、中国では非常に古い時代から重要な薬草として用いられてきました。
- 古典への登場: 中国の薬学書『本草綱目』にすでに収載されており、その薬効は古くから認められていました。
- 熱病(発熱)の治療: 伝統的な中国医学では、乾燥させた全草が「黄花蒿」あるいは「青蒿(セイコウ)」と呼ばれ、清熱薬(解熱薬)として使用されてきました。具体的には、結核性の熱や慢性の間歇熱、黄疸、神経性熱病、日射病、寝汗、そして後のマラリアなどに用いられていました。
- 皮膚疾患への外用: 全草の煎液は、寄生性皮膚病や田虫(たむし)の患部を洗う外用薬としても使われていました。
- その他の用途: 古くは苦味健胃薬としても用いられていたほか、種子は疲労や寝汗に用いられていた記録もあります。
特に紀元3世紀の医学書『肘後備急方』には「青蒿の絞り汁が病に効く」という記述があり、これが現代の科学的大発見へとつながる重要なヒントとなりました。
現代医学における革命:アルテミシニン
クソニンジンから抽出される主成分アルテミシニンの発見は、マラリア治療に革命をもたらしました。
- 発見と受賞: 2015年にノーベル生理学・医学賞を受賞した中国人研究者 屠呦呦(ト・ユウヨウ)氏は、伝統医学の知恵を基に、この植物からアルテミシニン(Artemisinin)を分離・抽出することに成功しました。これは、それまでの治療薬に耐性を持つマラリア原虫にも有効であり、現代科学と伝統医学の融合の成果として高く評価されています。
< 進む研究:新たな薬理作用と栽培技術>
アルテミシニンは主に葉と穂の部分に含まれます。その有用性から、さらなる研究が進められています。
栽培技術の研究: アルテミシニンの効率的な生産を目指し、土壌条件や組織培養、キトサンの葉面散布など、さまざまな技術を活用した研究が精力的に進められています。
新たな薬理作用: 近年の研究では、クソニンジン抽出物やアルテミシニンに抗酸化作用や抗炎症作用が報告されており、特にラットを用いた実験で肝臓保護作用や腎臓保護作用を持つ可能性が示唆されています。
<出典一覧>
京都大学理学研究科・理学部「マラリア治療の難しさとアルテミシニン」(ノーベル賞受賞者、アルテミシニン発見の背景、マラリア治療の重要性に関する記述)
クソニンジン – Wikipedia (学名、分類、和名の由来、特徴、生薬としての利用、アルテミシニンに関する記述)
熊本大学薬学部薬用植物園 薬草データベース – クソニンジン(古来の用途:清熱薬として発熱、日射病、寝汗、マラリアなど。寄生性皮膚病、種子の用途に関する記述)
山科植物資料館 – クソニンジン(キク科)(古来の用途:解熱薬として結核性の熱、慢性の間歇熱、黄疸、寄生性皮膚病への外用に関する記述)
薬草と花紀行のホームページ – クソニンジン(古典『本草綱目』への収載、古くから苦味健胃薬に用いたという記述)
公益社団法人 東京生薬協会 – クソニンジン(和名の由来、生薬名、薬用部分、用途、ノーベル賞受賞者に関する記述)
Chem-Station (ケムステ) – クソニンジンのはなし(ノーベル賞につながる歴史的背景、屠呦呦博士と古い薬学書『肘後備急方』に関する記述)
特定非営利活動法人 日本メディカルハーブ協会「ヨモギの植物学と栽培」(ヨモギ属の分類、中国での「青蒿」の呼称に関する記述)
J-GLOBAL 科学技術総合リンクセンター(クソニンジンに関する文献情報:アルテミシニン生産を目的とした栽培、組織培養、キトサン葉面散布など、研究テーマに関する記述)
中央動物病院「アルテミシア アンヌア(クソニンジン)の肝腎機能保護力を確認した論文」(アルテミシア・アヌアの肝臓・腎臓保護作用、抗酸化作用に関する記述)
当ホームページで使用している「クソニンジンの画像」は、写真の中又は写真下にkusoninjin.comと8pt以上の文字で表記いただければフリー画像として無料でご活用いただくことができます。